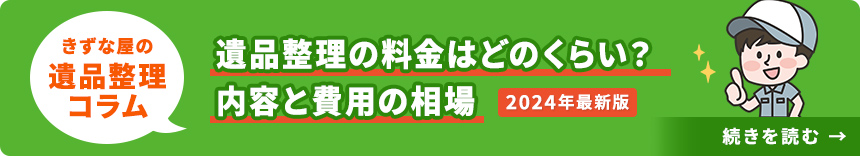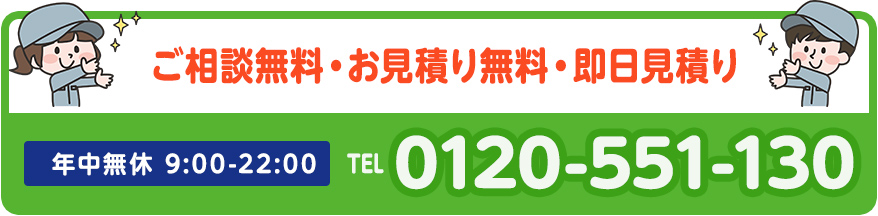更新:2024年11月15日
遺品整理や生前整理と聞くと、一般的には家財道具や家の整理を連想する方が多いのではないでしょうか?
ですがデジタル機器やオンライン上のデータも、整理しなければならない大切な遺品のひとつです。
近年はさまざまなデジタル機器が一般化し、写真や動画をデジタルデータとして保有している方が増えています。
一方で、個人情報として慎重に扱われるデジタルデータだからこそ、遺品整理でのトラブルの原因になってしまうケースも少なくありません。
今回は、そんなデジタル遺品の生前整理や整理方法について、詳しくお話しします。

3.デジタル遺品によって引き起こされるトラブル事例
3-1 必要なデータにアクセスできない
3-2 契約中のサービスが把握できない
3-3 スマホのデータが消えてしまった
3-4 見られたくないデータを遺族に見られてしまう
4.デジタル遺品を生前整理する方法
4-1 写真や動画は日頃のこまめな整理が効果的
4-2 見られてもいいデータと見られたくないデータを整理する
4-3 パスワードを控えておく
4-4 エンディングノートを用意しておく
5.デジタル遺品の整理の進め方
5-1 故人のデジタル機器を確認する
5-2 各デジタル機器のロックを解除する
5-3 データを確認する
5-4 確認したデータを整理する
5-5 デジタル機器を処分する
6.まとめ
>>【参考コラム】
1.デジタル遺品とは?
デジタル遺品とはその名の通り、写真や動画、メール、個人情報、連絡先などの、故人が遺したデジタルデータを指します。
場合によってはデジタルデータを保存しているデジタル機器そのものや、
デジタル機器を介して利用していたSNSなどのサービスアカウントなどを含むケースもあり、定義は明確ではありません。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
●パソコンやスマートフォン、タブレットなど(デジタル機器そのもの)
●パソコンやスマートフォンに保存されたデータ(写真、動画、連絡先など)
●SNSやインターネットバンキング、Webメールなどのデジタルアカウント
●動画や音楽、電子書籍の配信サービスなど、月額料金がかかるサブスクリプションサービスのアカウント
これらはいずれも故人の個人情報やプライバシー、財産、思い出などに関わる、遺産そのものです。
現実の写真や通帳などと同じように、普段から適切に管理・保存しておきましょう。
2.デジタル遺品の整理が必要とされる理由
デジタル遺品は他の遺品とは異なり、実体のないデジタルデータであるため、遺品としてはなかなか捉えにくいかもしれません。
ですが先述の通り、デジタル遺品には個人のプライバシーや思い出、財産なども含まれるため、立派な遺品そのものです。
したがってデジタル遺品に関しても、遺された遺族が困ってしまわないように普段から整理・管理しておくのが大切となります。
ですがデジタル遺品の場合、通常はデジタル機器内部に保存されており、パスワードなどによるロックを解除できなければ、たとえ遺族であろうとデジタルデータにアクセスできません。
またデータやアカウントに関しても、パスワードなどによって保護されているため、事前にパスワードを知らされていない限り、アカウント情報の確認すらできなくなります。
特にスマートフォンの中には、ロックの解除に失敗し続けると内部のデータが自動的に消去されてしまう仕組みが組み込まれている機種があるほか、専門業者でもロック解除が困難であるケースも少なくありません。
遺族がスムーズにデジタル遺産を処理できるよう、データそのものだけでなく、データへのアクセス方法や必要な情報に関しても整理しておくのが大切です。
3.デジタル遺品によって引き起こされるトラブル事例
とはいえ、デジタル遺品によって具体的にどのようなトラブルが引き起こされてしまうのか、うまくイメージできない方もおられるでしょう。
ここからは、デジタル遺品によって遺品整理時に引き起こされてしまうよくあるトラブル事例をご紹介します。
3-1.必要なデータにアクセスできない
写真は、スマートフォン(スマホ)やデジタルカメラで撮影し、保存するのが基本、という方も多いのではないでしょうか?
デジタルデータとして扱う写真は、パソコンやスマホがあればいつでも確認できますし、必要になれば印刷も可能で、とても便利です。
ですが逆を言えば、パソコンやスマホでデータにアクセスできなければ、写真の確認すらできなくなります。
自身の写真をすべてスマホに保存しているとしたら、葬儀の際の遺影も、スマホ内の写真から選ぶ必要が出てきます。
もし遺族がスマホのロックを解除できなかったら、遺影を用意できずに困ってしまう可能性が高いでしょう。
葬儀のために故人の友人や知人に連絡をする際に、スマホの内に保存された電話番号を確認する必要が出てくる可能性もあるでしょう。
実際そのような場合にスマホにアクセスできず、案内を送るのに苦労してしまったケースも少なくありません。
3-2.契約中のサービスが把握できない
近年はインターネットバンキングやネット証券など、パソコンやスマホから利用できる銀行口座や投資用口座が一般化しています。
口座を作る際も取り引きする際も、窓口にわざわざ出向く必要がなく、オンラインで気軽に手続きを済ませられるため、家族や親族が把握していない中で利用していた、というケースも少なくないでしょう。
デジタル遺産として情報が整理されていなければ、このような銀行口座や投資用口座の存在は、見つけ出すだけでもかなり難しくなってしまいます。
遺産分割が一通り済んだ後で口座が見つかったため、その分の分割協議が別に必要になってしまった、といったケースも少なくありません。
また動画や音楽の配信サービスや、定期的に冷凍食品を届けてくれるサービスなど、月額課金制のアプリやサブスクリプションサービスを利用している可能性もあります。
このようなサービスは存在を確認できないと契約を解除できず、いつまでも利用料の請求が続いてしまうため注意が必要です。
3-3.スマホのデータが消えてしまった
スマホの機種の中には、ロックを解除する際のパスワードを連続して規定回数失敗すると、通常の方法ではロックを解除できなくなるものや、データが初期化されてしまうものも存在しています。
ロック解除のパスワードがわからないからと、思い当たるものを入力して試していたら、故人の大切なデータが失われてしまった、というトラブルがあるので注意してください。
また月額課金のストレージサービスを解約したところ、中に保存されていたデータが失われてしまった、というケースも見受けられます。
デジタルデータではありませんが、事前に残高をチャージする必要があるQRコード決済サービスを利用していた場合、チャージ済みの残高に気づかずに放置してしまうケースも少なくありません。
3-4.見られたくないデータを遺族に見られてしまう
データを残す側の視点では、誰にも見られたくない、遺族にも秘密にしておきたいデータを、デジタル遺品の整理の一環として遺族が触れてしまい、見られてしまうケースが多いです。
秘密の内容次第では第三者に迷惑を掛けてしまうかもしれませんし、守秘義務や社外秘などの業務上の秘密に関わる内容であれば、社会的な問題に発展してしまうかもしれません。
見せたくないデータはあらかじめ整理しておき、見られないための工夫や対策を施しておく必要があるでしょう。

4.デジタル遺品を生前整理する方法
デジタル遺品による混乱を未然に防ぐには、生前からデジタル遺品を整理しておく必要があります。
とはいえ具体的に、どのように整理をすればよいのでしょう?
ここからは、デジタル遺品を生前整理する具体的な方法を、いくつかご紹介します。
4-1.写真や動画は日頃のこまめな整理が効果的
日常的に風景などの写真を撮っている方や、動画に残している方は少なくないかと思います。
このような日々増えていきやすい写真や動画は、日頃からこまめに整理しておくのが効果的です。
写真の種類ごとにフォルダを分けておく、家族や友人に共有したい写真とプライベートの写真を分けておく、不要な写真は消しておくなど、都度整理しておくよう心がけましょう。
写真の保存にストレージサービスを活用している場合は、家族に残したい写真をあらかじめ選別しておき、共有機能を利用してあらかじめシェアしておく方法があります。
ストレージサービスは本人以外のアクセスを認めていないサービスも多く、何かとトラブルになりがちです。
ですが事前に共有されているデータに関しては、遺族も苦労なくアクセスできるので安心できるので、ぜひ活用してみてください。
4-2.見られてもいいデータと見られたくないデータを整理する
デジタル遺品として残るデータは大きく、見られてもいいデータと見られたくないデータの2種類に分けられます。
これらを分けて整理・管理しておき、見られてもいいデータのみ家族に共有しておくのが、基本的な整理方法になるでしょう。
デジタル機器は個人情報を守るための仕組みが組み込まれているため、事前に対策をしておかないと、基本的に家族を含む第三者のアクセスは難しくなります。
したがって見られたくないデータに関しては、たとえば見られたくないデータを1つのデジタル機器に集約したうえで、そのデータに関しては触れてほしくない意思を伝えておくだけで、十分に守り切れるでしょう。
逆に見られてもいい、共有したいデータに関しては、家族が不自由なくアクセスできる状態を作っておく必要があります。
一部のデータだけ共有する場合には、見られたくないデータに関してはフォルダ単位でロックをかけるなどの工夫が必要になるでしょう。
いずれにせよデータごとに個別に対応できるよう、普段から見られてもいいデータ、見られたくないデータをしっかり整理しておくのが大切です。
4-3.パスワードを控えておく
パスワードは、デジタル機器やデータを保護するための典型的な手段です。
パソコンやスマホそのものだけでなく、アプリや各種サービスのアカウント情報にアクセスするのにも、基本的にパスワードが必要になってくるでしょう。
デジタル遺品の整理では、それらのパスワードを一覧化して控えておくのが非常に大切です。
パスワードがあれば、遺族によるデータ整理の負担を大きく減らせるでしょう。
パスワードだけでなく、サービス名やアカウント名など、アクセスするために必要な情報、アクセス方法などもまとめておく必要があります。
どのように扱ってほしいかも書き記しておくと、家族も対応がしやすくなるでしょう。
4-4.エンディングノートを用意しておく
生前からパスワードを共有しておくのに抵抗がある場合は、エンディングノートを用意して、その中にパスワード一覧をまとめておくのがおすすめです。
エンディングノートとは、自分自身に万が一があった場合に備えて、自分に関する情報や思い、希望、家族に伝えたい事柄、死後の手続きなどを書き記しておくためのノートです。
ノートの中には、銀行口座や利用中のサービスを一通り書き込める表を用意しているものもありますので、上手に活用してみてください。
必要に応じて加筆・修正するのも大切です。
情報が古いまま残らないよう、年に1回や半年に1度など、定期的に内容を確認するよう心がけましょう。
5.デジタル遺品の整理の進め方
遺族が故人のデジタル遺品を整理する場合には、以下のステップで処理していくのがおすすめです。
1.故人のデジタル機器を確認する
2.各デジタル機器のロックを解除する
3.データを確認し対処する
4.確認したデータに対処する
5.デジタル機器を処分する
それぞれ簡単に確認していきましょう。
5-1.故人のデジタル機器を確認する
まずは故人が所有していたデジタル機器を集めましょう。
SNSやサービスのアカウントは、どのデジタル機器からもアクセスできる可能性がありますが、そのデジタル機器の内部にだけ保存されているデータがあるかもしれません。
故人のデジタル遺品をもれなく整理するためにも、まずはすべてのデジタル機器を確認しておきましょう。
5-2.各デジタル機器のロックを解除する
次に、集めた故人のデジタル機器のロックを、1つずつ解除していきましょう。
特にスマホは多くのデジタル遺品が残されている可能性が高いため、優先して解除を試みるのがおすすめです。
パスワードなど、ロックの解除方法を故人が残していないか確認してみてください。
解除方法が残されていない場合は、解除をあきらめて機器ごと処分してしまうか、専門業者に解除を依頼するか、いずれかの対応が必要になります。
5-3.データを確認する
デジタル機器のロックを解除したら、データの確認をおこないましょう。
データの扱いについて故人の指示がある場合は、その内容に従ってください。
確認すべきデータには、以下のようなものがあります。
●写真や連絡先
●SNSやアプリなどの利用サービス
●銀行口座や証券口座など
5-4.確認したデータを整理する
確認したデータを整理し、適切に対処します。
たとえば葬儀などに使う写真や連絡先であれば、必要なときに使えるようデータを保存しておく、SNSのアカウントは削除しておく、サブスクリプションサービスは解釈しておく、などです。
また不要なデータに関しては、流出しないよう削除しておきましょう。
5-5.デジタル機器を処分する
データの整理が終わったら、デジタル機器そのものを処分しましょう。
デジタル機器を買い取ってもらう方法もありますが、ハードディスクなどのデータ保存媒体の扱いには注意してください。
削除したデータは専門技術を用いれば復元が可能なため、処分を依頼する場合、保存媒体については物理的に破壊・処分してもらえる業者を利用するのがおすすめです。
>>【参考コラム】
6.まとめ
デジタル遺品は形のない遺品であるため、どうしても整理の重要性に気づきにくい面があるかと思います。
ですがデジタル遺品にまつわるトラブルの多くは、利用サービスやパスワードの共有といった、
ちょっとした対策を実行するだけで防ぎやすい面があるのも、また事実です。
あなたの大切なデータや思い出、残された家族の利益を守るためにも、ぜひ生前整理を試してみてください。
専門家のきずな屋では、無料見積もりをはじめ、様々な方法でお客様の遺品整理をサポートしています。
遺品整理や生前整理、ゴミ屋敷問題など、どんな状況でも丁寧に対応いたします。
お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適なアドバイスとサポートをベテランスタッフが提供いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
この記事の監修者した人

株式会社 きずな屋 代表取締役 久保田満
遺品整理やゴミ屋敷片付けの現場を長年担当してきたベテラン中のベテラン。
遺品整理やゴミ屋敷片付けの現場を的確に把握し信頼性の高い見積もりをお客様に提示することが高く評価されている。日々丁寧な仕事を心掛け様々な現場へを周りお客様の故人との思いをより反映できるような遺品整理を目指している。
========================================
#遺品整理 #デジタル遺品 #不用品回収